ホームページ作成の費用相場について
いくらくらいが適切なの?
日本最大級のホームページ制作会社検索サイト
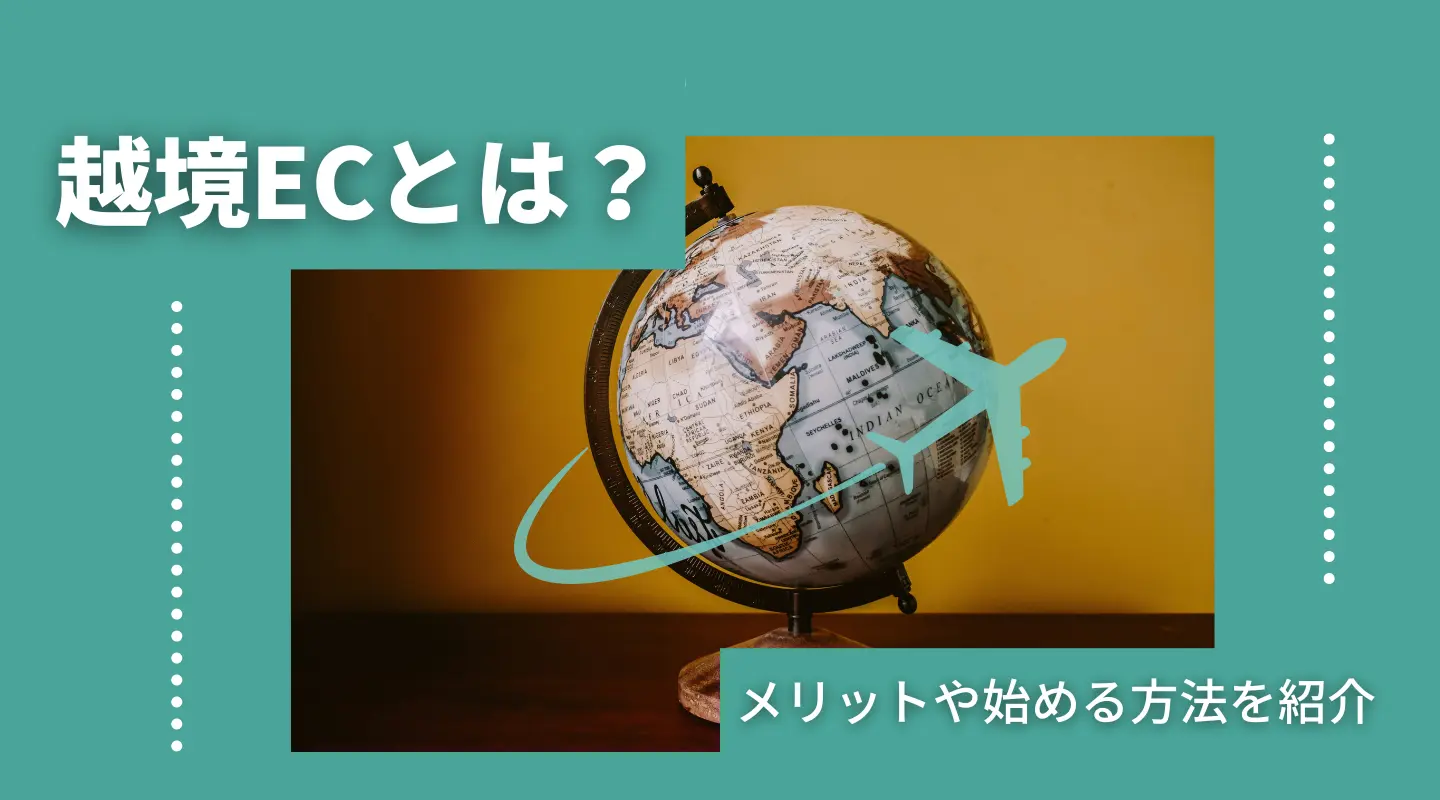
「越境ECって何?」
「越境ECを構築するときの注意点は?」
越境ECとは、国を越えて海外のユーザーと商品の取引を行うことです。
他国の市場に乗り出すため販路が広がり、上手くいけば大きな利益を得られます。
ただし、輸送コストが高額、ECサイトの多言語化が必要などの注意点もあるので、参入する前に越境ECについて理解しましょう。
本記事では以下について解説していきます。
本記事を参考に、越境ECを検討してください。
越境ECとは、海外に販路を広げ、商品やサービスを展開する電子商取引のことです。海外のユーザーに訴求できるため新規顧客を獲得でき、利益拡大が図れます。
インターネットや輸送技術の発展によりEC市場は世界的に拡大し続け、市場規模は500兆円を超えています。日本製の商品は海外でも人気が高いため、ニーズを見極めて参入すれば、大きな利益を得ることが可能です。
参考:「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」|経済産業省
そのため海外のECモールに出店したり、自社ECサイトを多言語対応したりと、多くの企業が越境ECに取り組んでいます。
外貨決済への対応や輸送路の確保など、多くのリソースが必要ですが、上手くいけば大きな利益が期待できます。
越境ECの市場規模は世界的に拡大し続けており、今後も拡大する見込みです。
経済産業省の調べによると、令和4年の中国事業者から日本への越境EC購入額は2兆2,569億円(前年比5.6%増)でした。また、アメリカからの越境EC購入額は1兆3,056億円(前年比6.8%増)です。
日本国内のBtoCのEC市場規模が22兆7,449億円なので、中国とアメリカだけでかなりの購入額だとわかります。
また、国ごとのEC市場規模の順位は以下のとおりです。
| 順位 | 国 | EC市場シェア率 |
|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 50.4% |
| 2位 | アメリカ | 18.4% |
| 3位 | イギリス | 4.5% |
| 4位 | 日本 | 3.1% |
| 5位 | 韓国 | 2.5% |
| 6位 | ドイツ | 2.1% |
日本のEC市場規模は世界で第4位となっています。中国やアメリカなど、上位の国へ進出すれば、さらなる集客が期待できるでしょう。
参考:「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」|経済産業省
越境ECには主に3つのメリットがあります。
それぞれくわしく解説していきます。
国内でECサイトを運営する場合、商材によっては競合が多く、激しい価格競争に巻き込まれる場合があります。
しかし越境ECで海外のユーザーをターゲットにすれば、ブルーオーシャンで販売を行える可能性が高いです。上手く競合の少ない国を見つけられれば、大きな利益を得られます。
販路を広げることで、新規顧客の獲得が狙えます。
新しい市場に進出すれば、それまでアプローチできなかった層へ訴求できます。また海外では日本製の商品に付加価値がつくこともあり、購入につながりやすいです。
特に中国は日本から商品を輸送しやすく、人口も多いため、越境ECに向いています。
顧客を増やせれば売上の基盤が大きくなり、事業拡大のチャンスも広がるでしょう。
もし海外に実店舗を増やそうとした場合、現地に責任者を派遣する、実店舗を作るなど、多大なコストが発生します。
一方で越境ECであれば、インターネット上に出店するだけなので、少ないリソースで実現可能です。
テナント代などの運用費用もかからず、人件費も安く済むため、大きなリスクを負わずに海外市場へ進出できます。
越境ECには以下のようなデメリットもあります。
それぞれくわしく解説していきます。
越境ECでは国内への配送よりも送料が高額になり、ユーザーが購入を躊躇う要因になります。輸送路の長いため紛失のリスクが高くなるなど、購入後のトラブルも起きやすいです。
そのため、梱包をコンパクトにする、現地に倉庫を設けるなどの対策が必要です。
また、信頼できる配送会社を選べば安心して輸送を任せられるでしょう。会社によっては、緊急出荷などのイレギュラーな対応をしてくれるところもあります。
越境ECは、取り扱う国の法律や規律に合わせて運営する必要があります。たとえばアメリカや中国で食品や化粧品、医薬品を販売する際は、特別な申請を行わなければなりません。
また、言語や決済サービスのローカライズが求められるなど、ECサイトの作り込みが必要です。対応にコストや時間がかかるので、注意しましょう。
越境ECには外貨決済のリスクが伴います。
たとえば、海外の決済システムの中にはセキュリティが脆弱なものもあり、サイバー攻撃の被害を受ける可能性があります。セキュリティ面で安全な外貨決済サービスの選定が必要です。
大手のサービスと標準で連携しているASPカートやパッケージもあるので、気になる人は調べてみてください。
また、為替変動による損失も考えられます。円建て決済を導入するなど、リスクを回避するための対策を講じましょう。
越境ECを始める方法は大きく3種類に分けられます。
それぞれくわしく解説していきます。
自社で越境ECサイトを構築、運営する方法です。多言語や外貨決済への対応など、必要な仕様を追加して制作します。
Shopifyのように越境ECの機能が充実したASPカートもあるため、制作方法によっては低コストで構築可能です。
また、ECモールよりも拡張性が高いので、自社の独自性をアピールしながら運営できます。越境ECでは日本製であることが強みになることも多いです。運用リソースはかかりますが、高い集客効果を得られるでしょう。
現地のECモールに出店・出品する方法です。AmazonやeBayなど、越境EC販売に対応したサービスに登録することで、海外のユーザーに商品を販売できます。
越境EC販売に対応している主なECモールは以下のとおりです。
企業のプラットフォーム上に出店・出品するため、施策を打たなくても集客が可能です。また現地への配送を委託できるサービスもあるので、少ないリソースで運用していけます。
しかし、自社ECサイトと比較すると拡張性が低い、手数料が高いといったデメリットもあるため注意しましょう。
運営代行業者に越境ECの業務を代行してもらう方法です。市場調査からECモールへの出店・出品、発送まで幅広い業務に対応してくれます。
代行費用はかかりますが、他の方法と比べて運営の手間やコストがかかりません。最低限のリソースで越境ECを行える方法です。
一方で、自社で店舗を運営しないため、顧客とコミュニケーションを取りづらくなるというデメリットがあります。
ユーザーに直接アプローチしてくれるサービスもあるので、顧客のロイヤルティを高めたい人は調べてみましょう。
構築や運営を行うリソースがなく自社ECサイトの開設に踏み出せない人は、越境ECに特化した制作会社に依頼するのも一つの手です。
海外市場にくわしく、サポートも充実しているため、成果を出せるECサイトを制作してくれます。
また、国の選定から輸送路の確保、現地での商品管理まで代行してくれる制作会社もあります。会社によってサービスは異なるので、気になる人は調べてみましょう。
越境ECにかかる費用は作り方によって異なります。
自社ECサイトを制作する場合、ASPカートによっては無料で制作可能です。一方、フルスクラッチで構築すれば1,000万円以上かかることもあります。
またECモールへ出典する場合もサービスによって費用相場が異なり、無料のものもあれば、月額で40万円以上かかるものもあります。
それぞれの作り方の費用相場について、くわしく解説していきます。
自社ECサイトの基本の構造は国内のECサイトと変わらず、国際配送や決済サービスなどの機能を追加して越境ECに対応させます。
制作費用は、対象とする国や追加する機能によって大きく異なります。
構築方法ごとの費用相場を表にまとめたので、参考にしてください。
| 構築方法 | 費用相場 |
|---|---|
| ASPカート | 無料~10万円 |
| オープンソース | 2万円~ |
| ECパッケージ | 10万円~ |
| クラウドEC | 10万円~ |
| フルスクラッチ | 500万円~ |
自社構築する場合は、ASPカートやECパッケージなど各サービスのホームページで料金を確認できることが多いです。制作会社に依頼する場合は見積り依頼をしましょう。
ECモールへの出店は、サービスごとに費用形態が違います。代表的なサービスの費用を表にまとめたので参考にしてください。
| サービス名 | 費用 | 手数料 |
|---|---|---|
| Amazon | 【小口出品費用】 1商品につき0.99ドル 【大口出品費用】 月額39.99ドル |
小口出品 8~15% 大口出品 8~15% |
| eBay | 【月額】 無料~約3,000ドル |
落札手数料 5%~15% PayPal手数料 4.1%+40円 |
| 天猫国際 (T-MALL GLOBAL) |
【初期費用】 5万元~15万元 【年額】 3万元~6万元 |
0.5~5% |
| au Pay マーケット | 【月額】 5,280円 |
4.5~9%(コミコミ出店プランの場合) |
複数のプランがある場合は、プランごとの特徴を理解した上で出店することが大切です。たとえば天猫国際は、店舗形態や商品ジャンルに応じて初期費用、商品の出品数に応じて年額が異なります。
越境ECの運用にかかる費用は、ECサイトの月額費用や手数料以外に、以下の2点が考えられます。
もし運営代行業者に依頼する場合、代行費用が発生します。業者によって支払い方法はさまざまで、成果報酬型では売上の5~10%、固定報酬型では月額1万~10万円が相場です。また月額に加えて、売上が発生した分だけ手数料が生じる複合型という方法もあります。
また、必ず発生するのが商品の輸送費です。運送会社によって価格は変わりますが、遠い国になるほど輸送費用は高額になります。
中国へ越境ECを行う場合は、保税区を活用して輸送コストの削減が可能です。
保税区とは、海外からの輸入品を、関税などの税金をかけずに保管しておける区域です。日本から中国までの輸送を一回で済ませられるため、輸送コストを下げられます。
また、現地の倉庫から発送することで、配送料を抑えつつ短い日数で購入者に配送可能です。
一方で、保管するコストが発生するため、在庫を抱え込むことになるリスクもあります。ある程度の安定出荷が見込める場合に利用しましょう。
越境ECを始める際は、事前に以下4点の確認が重要です。
国によっては文化の違いで商品が売れない場合があります。単に人口の多さや越境ECの始めやすさで国を選ぶのではなく、商品に対するニーズの事前調査が大切です。関税や輸送費用も加味して、利益が出るかどうか確認してください。
また、取り扱う商品が越境ECに適しているかも調べましょう。輸送しやすいか、海外への販売に対応しているかなどの調査が必要です。香水や喫煙用ライターなど、日本からの輸出が制限されている商品もあるので注意してください。
国ごとに法律や規制もさまざまです。特定の商品の輸入を厳しく制限しているところもあるため、問題なく販売できるか調べてみましょう。たとえばEU諸国に食品や化粧品を輸出するには、各国で特別な申請が求められます。
また越境ECの構築方法によって、かかる手間や運用コストが異なります。高品質な自社ECサイトを作っても、リソースが割けず運用に支障を出してしまっては意味がありません。効率的に越境ECを運営していくために、事前に人員と予算を明確にしてください。
自社で越境ECに対応したECサイトを制作する場合は、以下の構築サービスの利用がおすすめです。
それぞれくわしく紹介します。

出典:Shopify
ShopifyはカナダのShopify Inc.が開発したASPカートです。
50の言語と130ヵ国以上の通貨に対応しており、世界175ヵ国で利用されています。
また配送手配や通貨換算を自動で行ってくれる機能など、海外向けの機能が多いです。日本のキャリア決済のように、各国の独自の決済方法を100種類以上追加できるため、さまざまな国と越境ECを行えます。
さらに、広告運用や分析に役立つ機能も豊富なので、集客しやすいです。専門家のサポートが受けられるコミュニティもあるため、運用に不安がある人でも安心して利用できます。
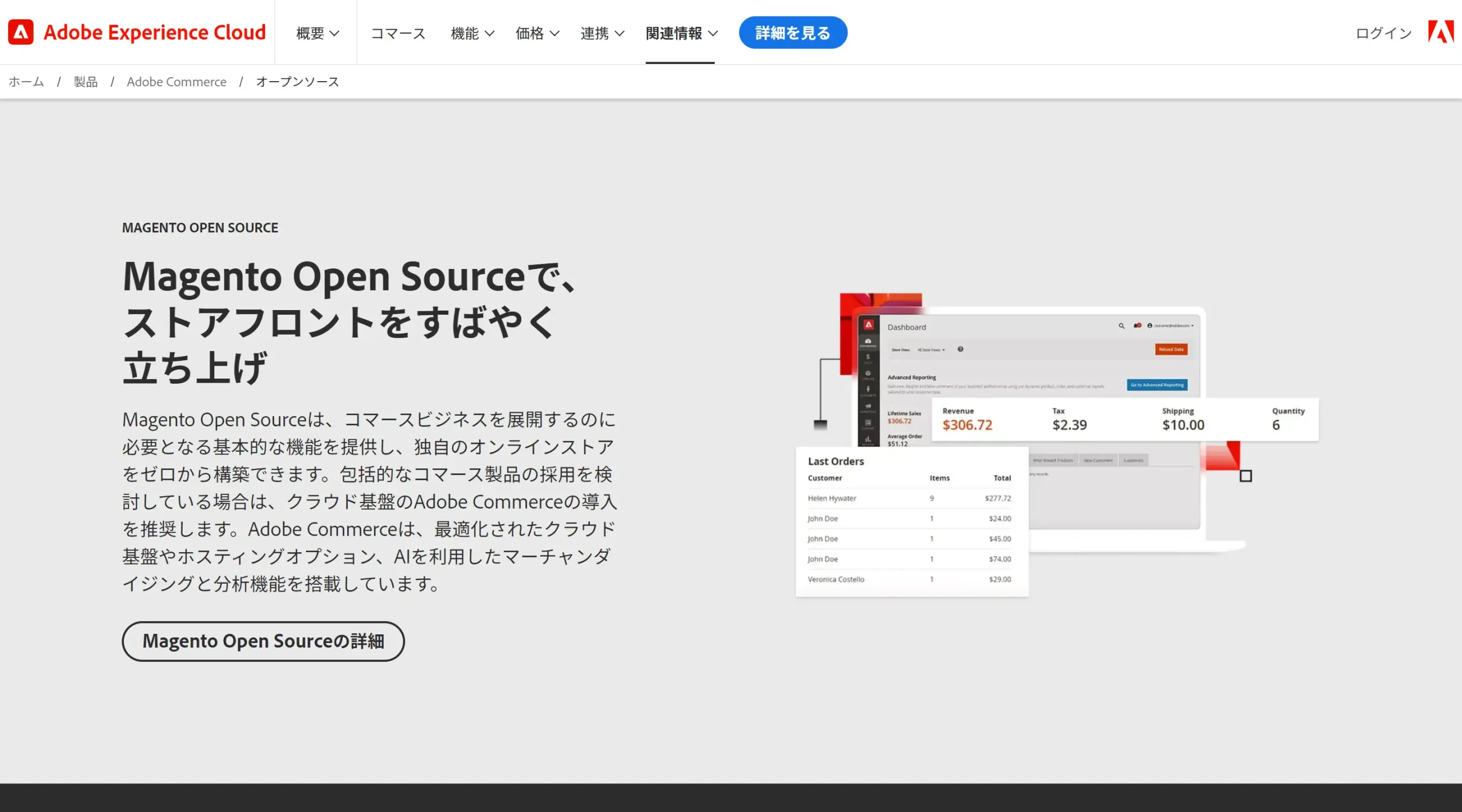
Magento Open Sourceは、Adobe Inc.が提供しているオープンソースです。
柔軟にカスタマイズできるため、独自性の高いECサイトを作れます。
デフォルトの言語だけで20種類以上用意されており、越境EC向けの機能も多数用意されています。たとえば、各国の税制や為替ルートに応じた価格計算を行う機能を追加可能です。
また、クレジットカード業界のセキュリティ基準であるPCIDSSを取得しているため、情報漏洩やウイルス侵入の心配もありません。
さらに、複数のサイトを一元管理できる仕様になっており、国ごとにECサイトを分けて2ヵ国以上との越境ECも可能です。アメリカの州ごとの税制やEC諸国のGDPRなど、各国の法律や規制にも対応しているため、効率的に事業を拡大していけるでしょう。
複数の国に越境ECを展開しながら、事業を拡大していきたい人におすすめです。
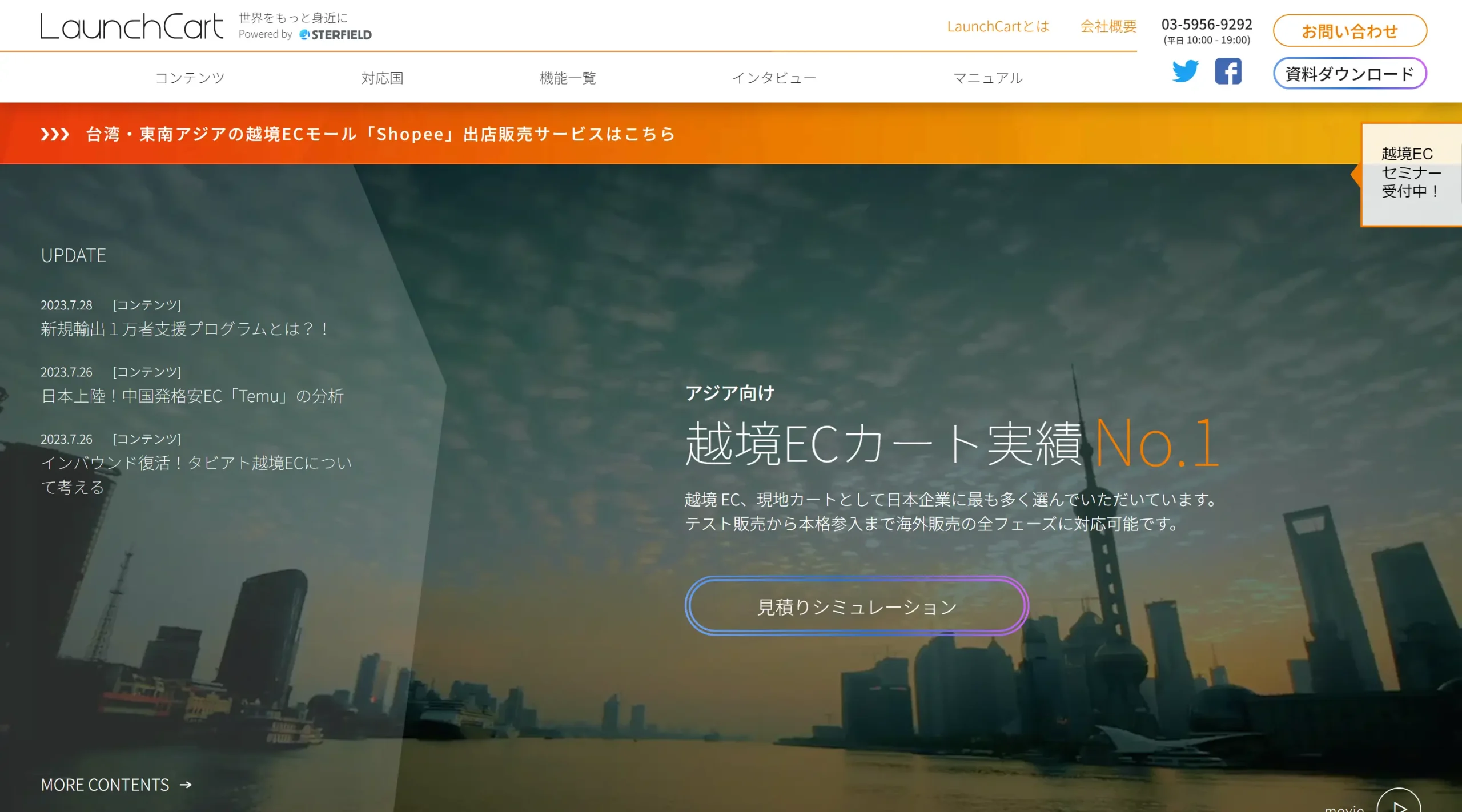
出典:LaunchCart
LaunchCartはスターフィールド株式会社が提供するクラウドECサービスです。
アジアを中心に、以下のような国との越境ECに対応しています。
世界の通貨の90%以上である160通貨が利用でき、さまざまな国への販売が可能です。地域ごとに表示する通貨を決められるため、複数の国に対して訴求していけます。
また、SEO対策や分析に役立つ機能を搭載しているので、集客にも強いです。コールセンターや在庫管理システムとの連携もできるため、効率的に運用していけるでしょう。
アジアを中心に複数の国の市場へ進出したい人におすすめです。
越境ECとは、国境を超えて行う電子商取引です。
市場が大きい海外のユーザーに訴求することで新規顧客を獲得し、売上向上を図ります。海外に店舗を作る必要がないため、効率的に事業を拡大していけるでしょう。
一方で、国に合わせた対応が求められたり、外貨決済のリスクを考慮する必要があったりと、注意点も多いです。進出する国や開設方法は慎重に決める必要があります。
EC市場は世界中で拡大を続けています。綿密な事前調査の上、適切な越境ECを始められれば、大きな成果が期待できるでしょう。