ホームページ作成の費用相場について
いくらくらいが適切なの?
日本最大級のホームページ制作会社検索サイト
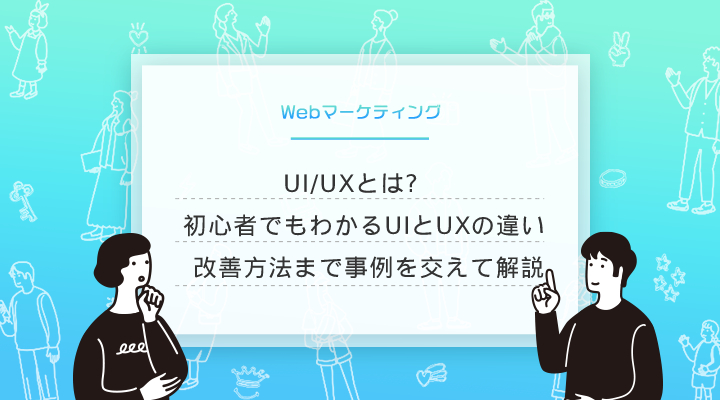
「UI/UXって何?」
Web業界に入って間もない方は、耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
UIとは、ユーザーと商品・サービスの接触面を指す言葉です。一方、UXは、ユーザーが商品やサービスを通して得る体験の全てを指します。Webサイトやアプリのみならず、商品やサービスの開発・改善に携わる方なら押さえておくべきポイントです。
本記事では、
について解説していきます。正しく理解し、Webデザインや商品・サービスの開発などの場面で活かせるようにしましょう。
ひとくくりで表現されることが多いUIとUX。字面が似ているため混同されることもありますが、異なる意味を持っています。とはいえ、UIとUXは対立しているわけではなく相互に影響を与える存在です。それぞれの概念と関係性について詳しく解説します。
UI(User Interface/ユーザーインターフェース)とは、ユーザーと商品・サービスの接触面を指します。
Webサイトの場合、スマホやPCに表示されるデザインやフォントなどのユーザーが視覚的に接する要素のすべてがUIにあたります。
UX(User Experience/ユーザーエクスペリエンス)とは、ユーザーが商品やサービスを通して得る体験の全てを指します。
Webサイトで商品を購入した場合、
といった、商品やサービスを利用することで生まれる感情を含む体験のすべてがUXにあたります。
UIはUXが意味を成す領域の一部であり、UIは優れたUX実現のための重要な要素です。
ユーザーに良い体験をしてもらうには、ユーザーの心理を理解したUIが必要不可欠です。ユーザーとの接点であるUIを蔑ろにして、使いづらかったりわかりづらかったりするUIを採用してしまうと、その他の体験がいくら優れていてもUXの質は下がってしまいます。
ただし、UIがUXのすべてでは無いということに注意が必要です。ここからはUIとUXの関係性に関する3つの注意点を解説します。
ユーザーが商品やサービス、利用するWebサイトを選択とき、UIの良し悪しだけが決定要因となることは滅多にありません。むしろUIが多少劣っていてもUXが優れているものが選ばれてきました。
商品やサービスがあふれるほど存在する現代では、人々の目は肥え表面的な部分だけが優れていても満足してもらえません。人々から評価を得られるものにするには、それらを使ったときに得られる体験、つまりUXで差をつけるしかないのです。
表面的なUIの改善は、簡単に真似をされてしまい差別化ができなくなってしまうため避けるべきです。
UXの改善は仕組みを伴うことがほとんどで、かなりの労力が必要なため気が進まないという方も多いでしょう。しかし、根本から見直すことより独自性が高く、誰にも真似できないものに。
競合が多く存在する市場で優位性を得るには優れたUXであることが必須条件といえます。
紙の新聞が年々発行部数が減少しているのに対し、ニュースアプリはどんどん勢力を伸ばしています。
新聞業界が確立された形にとらわれ、ユーザーのニーズとのギャップが生じ始めたところに、しがらみのない新規参入者(ニュースアプリ)がうまく現代のニーズとマッチしたことで起こった現象です。
この現象はどの業界においても起こり得ることで、ニーズの変化にいち早く気づき、柔軟な発想を持って商品やサービスを変化させていくことが鍵となります。
日本国内の利用者が8600万人(2021年3月現在)を超えるメッセンジャーアプリのLINEは、若者からお年寄りまでが簡単に使うことができるようなUIデザインにしたことで、既存のメールアプリよりも気軽なコミュニケーションを可能にしています。
具体的には、従来のメールアプリでは会話の流れを振り返ろうと思うと1つ1つのメールを開いて確認する必要がありました。LINEでは、自分と相手のメッセージが時系列順で縦に並んで表示されるので手間が省けるうえ、会話の流れが把握しやすいという利便性があります。
また、言語に頼らないコミュニケーションを可能にするスタンプ機能やグループチャットは、コミュニケーションの負担を軽減した要素の1つです。
このように、従来のメールアプリでユーザーが潜在的に抱えていた「使いづらさ」を改善したことが優れたUXに繋がり、爆発的なヒットを記録しています。
衣料品や雑貨を扱うECサイトのフェリシモは、休眠顧客に目をつけUX改善を行ったことで会員の離脱率を大幅に引き下げることに成功しています。
もともとフェリシモは休眠顧客に郵便によるDMを送付していたが成果が上がりませんでした。
そこで、ツールを用いてDMを送ったユーザーの行動をみると、
ということがわかり、「パスワード照会」に大きな問題があったことに気づきます。そこから、パスワードリマインダーの流れを改善したことで、年間1万人の離脱防止に繋がりました。
このように、思わぬところで顧客を逃しているケースはよくあります。やみくもに施策を行ったところでそう簡単には状況は改善できません。
フェリシモのケースでは、ツールを使ったことで原因を見つけ出すことができました。自社で行う分析に限界を感じたらツールを用いるのも効果的な手法の1つです。
UXデザインは、
①ゴールを決める
②ターゲットユーザーの分析
③設計・導線の見直し
④データの収集
⑤PDCAを繰り返す
という順で改善していきます。
ここからは、それぞれの手順を詳しく解説します。
まず初めに、UXデザインのゴールを決めましょう。
「なぜUXデザインの改善が必要だと感じたのか」「UXデザインを改善することで何を目指すのか」という点を明確にすることで、方向性が曖昧になることを防げます。
例えば、
など、Webサイトや商品・サービスによってそれぞれ異なるものになるはずです。
次に、ターゲットユーザーの分析を行います。
UXデザインの改善において最も大切なのは、ユーザー目線で考えることです。おしゃれさや新しさを追求したところで、ユーザーに使いにくいと感じさせてしまっては意味がありません。デザイナーの自己満足になってしまわないよう注意が必要です。
では、ユーザー目線で考えるにはどうすれば良いのか。おすすめはペルソナを活用することです。
ペルソナとは、商品やサービスの利用者の代表的な特徴を併せ持った架空の人物のこと。ペルソナを設定することで、ユーザーの行動や感情まで想像することができ、何を求められているかが明確になります。
また、ユーザーの行動1つ1つを深堀りするためのツールとして、カスタマージャーニーマップがおすすめです。
カスタマージャーニーマップがあると、ユーザーがサイトや商品などを利用する一連の流れを可視化できるため、改善すべきポイントを絞ることができます。
実際に商品やサービスを見直し、ユーザーの分析で得た気づきを落とし込みましょう。
Webサイトの設計や導線を見直す際は、アクセス解析でわかる指標の中でも「離脱率」「滞在時間」に着目することで改善すべきポイントを見つけやすくなります。
また、UXを改善するうえで知っておくべき指標の1つが「Web Vitals(ウェブバイタル)」です。
これは、Googleが提唱した「優れたUXデザインの指針」で、その中でも特に重要な3つの指標を「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」として2020年5月に発表されました。以下の項目が挙げられています。
コアウェブバイタル
これらの指標は、2021年6月より検索ランキングに関わるようになりました。知らずにマイナス評価を受けてしまうことが無いようしっかり理解しておきましょう。
改善して終わりではなく、データを集めて分析しましょう。
Webサイトのコンバージョン数や商品の売上といった数値として把握できる「定量データ」と、数値で表せない質的な部分である「定性データ」の両方を分析することで、正しく効果を測ることができます。
定性データを集めるための方法として「ユーザーインタビュー」がおすすめです。
ユーザーインタビューとは、実際に商品やサービスを利用しているユーザーに対して質問し、回答してもらう形で意見を聞き取るリサーチ手法です。回答者が自由に意見を発言できるよう「オープン・エンド型」の質問をすることで、潜在ニーズを引き出すことが期待できます。
ユーザーインタビューでは、行った施策の効果を知れたり、次に行うべき施策のヒントを得ることができるので、施策を行う前後のどちらで行っても効果的です。
PDCAを繰り返すことで、更なるUI/UXデザインの改善に繋げましょう。
優れたUI/UXデザインの条件は、時代の変化に伴って変わっていきます。常にユーザーに満足してもらうためには改善の手を止めないことが重要です。
UI/UXは、Webサイトだけでなくどの分野においても必要不可欠な概念です。
UIの表面的な改善にばかり注力するのではなく、常にユーザーの目線に立ち、UXを改善し続けることでユーザーからの評価が高い商品やサービスに成長することができます。
本記事でUI/UXについての理解を深め、Webサイトや商品・サービスの改善に役立ててみてはいかがでしょうか。